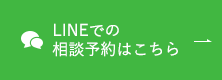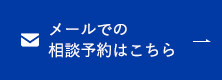2025/09/26 コラム
慰謝料の返還請求:支払いが法的に争われるケース
はじめに:合意の終局性と例外の原則
不貞行為に関する慰謝料の支払いは、一度当事者間で合意が成立し、金銭の授受が完了すれば、原則としてその問題は終局的に解決されたものと見なされます。この「合意の終局性」は、法的な安定性を保つ上で重要な原則です。しかし、この原則は絶対的なものではありません。合意の内容そのものや、合意が成立した経緯に重大な法的問題が存在する場合、支払った慰謝料の返還を求めることが法的に認められることがあります。
本章では、一度支払った慰謝料の返還が認められる例外的な状況、特に「公序良俗違反」と「不法原因給付」という二つの重要な法的概念に焦点を当てて、その要件と具体的な対応策を詳述します。
公序良俗違反による合意の無効(民法第90条)
公序良俗違反の法理
民法第90条は、「公の秩序又は善良の風俗」に反する法律行為を無効と定めています。これは契約自由の原則の限界を示すものであり、当事者がいかなる内容の合意をしようとも、その内容が社会の基本的な倫理観や道徳観から逸脱する場合には、法的な保護を与えないという趣旨です。不貞慰謝料の文脈では、この規定は主に慰謝料の金額が社会通念を著しく逸脱し、賠償というよりも制裁や脅迫に近い性質を帯びている場合に適用されます。
「社会通念上、著しく高額」とは
慰謝料の金額がどの程度であれば「著しく高額」と判断されるかについては、一律の基準は存在しません。裁判所は、個別の事案における様々な事情を総合的に考慮して判断します。考慮される主な要素には、不貞行為の期間、態様、婚姻期間、当事者の年齢や社会的地位、支払う側の資力、そして合意が成立した際の状況(脅迫的な言動の有無など)が含まれます。
実際の裁判例を見ると、司法の判断基準がより明確になります。例えば、離婚協議書で定められた1500万円の慰謝料について、裁判所はこれを高額であると認め、公序良俗に反するとして、その効力を450万円の範囲に限定した事例があります。この判断は、契約全体を無効にするのではなく、社会的に妥当と考えられる範囲で効力を認める「一部無効」の法理を適用したものです。同様に、接触禁止条項の違反に対する違約金として1000万円を定めた合意について、裁判所は「著しく合理性を欠く」として150万円を超える部分を公序良俗違反で無効とした例もあります。
一方で、500万円や1000万円といった高額な慰謝料の合意が、事案の悪質性などを理由に有効と認められたケースも存在します。これらの事例からわかるように、裁判所の判断は単なる金額の大小ではなく、その金額が事案の重大性と比較して不相当に過大であるか否かという実質的な観点から下されます。
不法原因給付の法理(民法第708条)
不法原因給付とは
民法第708条は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と定めています。これは、違法な目的のために自ら財産を提供した者に対して、法は助力をしないという「クリーンハンズの原則」を表明したものです。例えば、犯罪の対価として支払った金銭や、賭博で負けた金銭の返還は、この規定により認められません。
慰謝料支払いへの適用と誤解
ここで注意すべきは、不貞行為に対する慰謝料の支払い自体は、原則として「不法な原因」には該当しないという点です。不貞行為は不法行為であり、それに対する損害賠償としての慰謝料支払いは、法的に認められた正当な行為です。
しかし、慰謝料請求の態様が詐欺や強迫といった違法な手段を用いて行われた場合、状況は複雑になります。例えば、実際には不貞行為がなかったにもかかわらず、虚偽の事実を突きつけて慰謝料を支払わせたようなケースでは、その給付の原因に「不法」な要素が含まれていると評価される可能性があります。
但し書きの重要性
民法第708条には、「ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない」という重要な但し書きがあります。これは、不法性がもっぱら金銭を受け取った側(受益者)にのみ存在する場合、支払った側(給付者)は返還を請求できることを意味します。先の例で言えば、詐欺によって慰謝料を支払わされた場合、不法性は詐欺を働いた受益者側にのみあるため、給付者は支払った金銭の返還を求めることが可能です。さらに判例では、給付者の不法性よりも受益者の不法性が著しく大きい場合にも、衡平の見地から返還請求を認める傾向にあります。
返還請求を受けた際の具体的な対応策
慰謝料の返還を求める通知が相手方から届いた場合、感情的に反発するのではなく、冷静かつ法的に対応することが不可欠です。まず、相手方が主張する返還理由が、公序良俗違反なのか、錯誤や詐欺によるものなのか、あるいは不法原因給付の法理に基づくものなのかを正確に把握する必要があります。
次に、慰謝料請求が正当であったことを裏付ける証拠を再整理します。これには、不貞行為の証拠(メール、写真、調査報告書など)、慰謝料額について合意した際の経緯を示す書類(合意書、念書)、交渉時の録音などが含まれます。特に、合意金額が相場から見て高額である場合には、なぜその金額で合意するに至ったのか、その合理的な理由を説明できるかが重要となります。
相手方の主張に法的な根拠が乏しいと判断される場合でも、安易に無視することは避けるべきです。弁護士などの専門家に相談し、法的な観点から自らの請求の正当性を主張し、必要であれば交渉や訴訟を通じて解決を図ることが賢明です。
長瀬総合のYouTubeチャンネルのご案内
法律に関する動画をYouTubeで配信中!
ご興味のある方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。
その他のコラムはこちらからお読み下さい