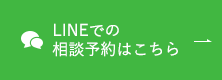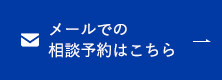2025/10/13 コラム
離婚協議書の「今後一切請求しない」条項(清算条項)の注意点
清算条項の目的と原則的な効力
離婚協議書や公正証書には、通常、末尾に「清算条項」と呼ばれる条項が設けられます。これは、「本協議書に定めるもののほか、当事者間には何らの債権債務も存在しないことを相互に確認し、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに金銭その他の請求を一切しない」といった内容の合意です。
この条項の目的は、離婚に関するすべての問題をこの合意によって終局的に解決し、将来再び紛争が蒸し返されることを防ぐ点にあります。適切に合意された清算条項は、原則として法的に有効であり、当事者を拘束します。したがって、一度この条項に合意すれば、後から「やはり慰謝料が欲しい」「財産分与が少なかった」といった追加の請求をすることは、原則としてできなくなります。
しかし、この原則には、当事者の権利を不当に害することを防ぐための重要な例外が存在します。
例外①:合意の前提となった事実に錯誤があった場合
清算条項の効力が及ぶのは、あくまで合意当時に当事者が認識していた、あるいは認識し得た事柄に限られます。もし、合意の重要な前提となる事実について、一方の当事者が知らされていなかった場合、その事実に関する部分については清算条項の効力が及ばない、あるいは条項自体が無効と判断されることがあります。
隠された不貞行為
最も典型的なのが、離婚後に相手の不貞行為が発覚したケースです。離婚当時に不貞の事実を全く知らず、したがって慰謝料を請求するという発想自体がなかった当事者が、清算条項に合意したとします。この場合、慰謝料請求権を放棄する意思はなかったと解釈され、清算条項の効力は慰謝料請求には及ばないと判断される可能性があります。
実際に、夫が不貞相手の妊娠という重大な事実を隠して妻に清算条項付きの離婚届に署名させた事案で、裁判所は妻の「要素の錯誤」(契約の重要な部分に関する勘違い)を認め、清算条項を無効とし、妻からの慰謝料請求を認めた判例があります。
隠された財産
同様に、相手方が共有財産を意図的に隠しており、その存在を知らないまま財産分与に合意し、清算条項を受け入れた場合も、後に発覚した財産については、改めて分与を請求できる可能性があります。
例外:放棄できない子どもの養育費請求権
清算条項には、効力が及ばない例外があります。それが「子どもの養育費」です。
法制度は、当事者である夫婦間の個人的な権利(慰謝料や財産分与)と、子どもの生存に関わる権利(養育費)とを明確に区別しています。養育費を受け取る権利は、親の権利ではなく、本質的には子どもの権利です。そして、民法第881条は、この扶養を受ける権利を親が勝手に「処分することができない」と定めています。
この規定は、子どもの福祉を最優先する強い公的要請を反映したものです。したがって、たとえ離婚協議書で「養育費は一切請求しない」と明記し、清算条項に合意したとしても、その合意は法的に無効です。子どもを監護している親は、子どもの代理人として、将来、経済状況の変化などに応じて、相手方に対して養育費の支払いをいつでも請求することができます。家庭裁判所の実務も、この考え方で一貫しています。
長瀬総合のYouTubeチャンネルのご案内
法律に関する動画をYouTubeで配信中!
ご興味のある方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。
その他のコラムはこちらからお読み下さい