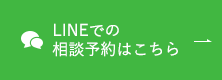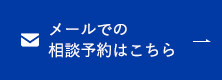2025/10/10 コラム
不倫発覚後に作成された念書・誓約書の法的効力
書面による合意の原則的な有効性
不貞行為が発覚した後、当事者間で作成される念書や誓約書は、適切に作成されていれば法的に有効な契約として扱われます。これらの書面は、不貞行為の事実を当事者が認めたこと(事実認定)、慰謝料の金額や支払条件、そして将来の接触禁止といった約束事を明確にする重要な証拠となります。口約束だけでは後日「言った、言わない」の争いになりがちですが、書面に残すことで、合意内容が明確化され、将来の紛争を予防する効果が期待できます。
合意が無効・取消しとなり得る場合:強迫による意思表示(民法第96条)
念書や誓約書が法的に有効であるためには、それが当事者の自由な意思に基づいて作成されたことが前提となります。もし一方が他方を脅迫し、恐怖心から無理やり署名・押印させたような場合には、その意思表示は法的に保護されません。
強迫の法的定義
民法第96条1項は、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」と定めています。ここでいう「強迫」とは、単に精神的なプレッシャーを感じたというレベルでは足りません。法的に強迫と認められるためには、相手方による違法な害悪の告知(例えば、生命、身体、財産、名誉などに対して危害を加える旨を告げること)があり、それによって表意者が畏怖(恐怖心)を抱き、その結果として不本意ながら意思表示(署名・押印)を行った、という因果関係が必要です。
強迫に該当しうる具体例
裁判例では、以下のような状況が強迫と判断される要素となり得ます。
- 複数人で相手を取り囲み、威圧的な雰囲気の中で署名を迫る。
- 「署名しなければ、会社や家族にすべてを暴露する」と告げ、相手の社会的生命を脅かす。
- 大声で怒鳴りつけたり、机を叩いたり、あるいは直接的な暴力を振るったりして、相手を精神的・肉体的に追い詰める。
重要なのは、慰謝料を請求する側が感情的になり、厳しい言葉で相手を追及すること自体が直ちに強迫となるわけではないという点です。正当な権利行使の範囲を逸脱し、社会通念上許容されない違法な手段を用いたかどうかが判断の分かれ目となります。
取消しの効果
強迫によってなされた契約は、当然に無効となるわけではありません。強迫された側が、相手方に対して「強迫を理由に契約を取り消す」という意思表示をすることで、初めてその効力が失われます。そして、一度取り消された契約は、初めから存在しなかったものとして扱われます。
執行力の確保:公正証書の活用
私人間で作成された念書や誓約書は、それ自体に裁判の判決のような強制執行力はありません。つまり、相手が慰謝料の支払いを怠ったとしても、その念書だけを根拠に直ちに相手の財産(給与や預金口座)を差し押さえることはできません。差し押さえを行うためには、別途訴訟を提起して勝訴判決を得る必要があります。
この手続き的な手間と時間を短縮できるのが「公正証書」です。
公正証書とは
公正証書とは、公証人という法律の専門家が、当事者間の合意内容を確認した上で作成する公的な文書です。その信頼性は非常に高く、強力な証拠能力を持ちます。
強制執行認諾文言の威力
公正証書の最大のメリットは、「強制執行認諾文言」を付すことができる点にあります。これは、「本契約に定められた金銭債務を履行しない場合は、直ちに強制執行を受けても異議はありません」という債務者の陳述を記載する条項です。この文言付きの公正証書があれば、万が一支払いが滞った際に、訴訟を経ることなく、直ちに裁判所に対して強制執行の申立てを行うことが可能となります。これは、慰謝料の支払いを確実にする上で強力な手段です。
公正証書の限界
ただし、公正証書も万能ではありません。公正証書が主に効力を発揮するのは、金銭の支払いに関する約束事です。例えば、「二度と不貞行為をしない」「相手の配偶者に接触しない」といった非金銭的な約束については、たとえ公正証書に記載したとしても、その履行を法的に強制することはできません。また、前述したように、合意内容自体が公序良俗に違反する場合(例えば、法外な違約金)や、強迫によって作成された場合には、たとえ公正証書化されていても、その条項の無効や契約の取消しを争うことは可能です。公正証書は、あくまで「法的に有効な合意」の執行力を高めるためのツールであると理解することが重要です。
長瀬総合のYouTubeチャンネルのご案内
法律に関する動画をYouTubeで配信中!
ご興味のある方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。
その他のコラムはこちらからお読み下さい